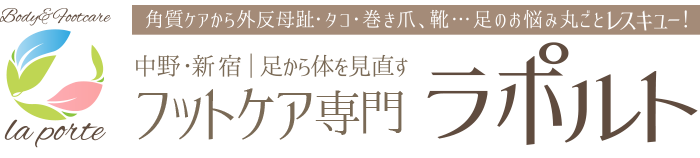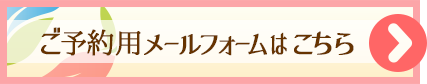なぜ私達はハイヒールを履くの…?そこには履く理由がある
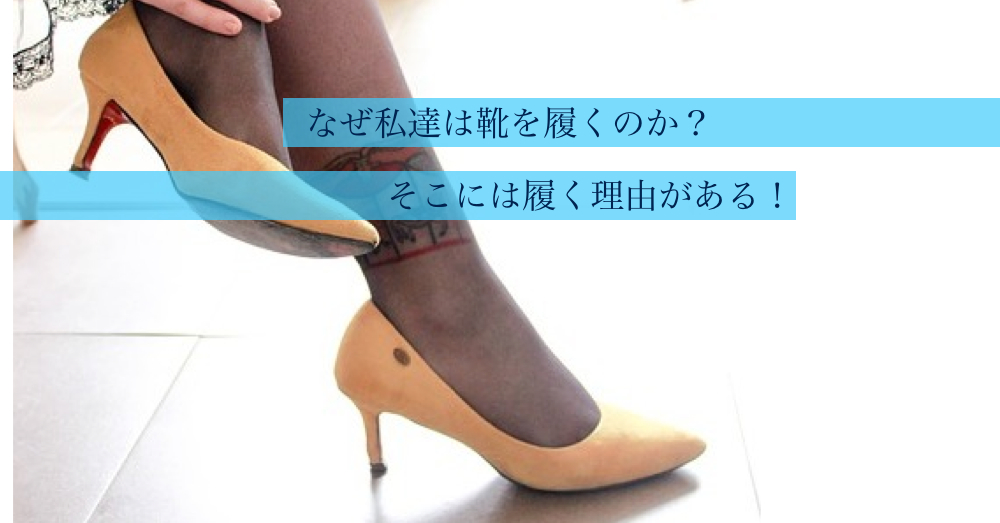
なぜ履くのか?そこにある理由
どうして私達は歩きにくく、足に悪いといわれるヒール靴を履くのでしょうか。
考えた事はありますか?
- 女性だから
- カッコよく見えるから
- ファッションだから
- 足が細く見えるから
- 身長が低いので履いています
中には仕事でどうしようもなくという方もいらっしゃいます。
ただ、この選択肢が沢山ある日本では、この答えが多いのではないでしょうか
ヒール靴を履きたいから、履く!

もちろんそうなのですが、実はそれでは答えになっていません。
ヒール靴を履くそこには「履く理由」があります。
靴とは何なのか?
私はオーダーメイドでインソール(靴の中敷)も製作しています。
インソール製作では師匠がいるのですが、靴に関してはとても厳しい人でした。
「こんなの靴じゃないよ!」
お客様の靴にダメなところがあると、面と向かってそう言っていました。
カカトの高いヒール履、脱げそうになるミュール、ヨレるズック靴…お客様にけちょんけちょんにダメ出しをする場面に何度も立ち会いヒヤヒヤしました。
顔にはまさに、なんでヒール靴なんてはくのか?と書いてあるようでした。
足の健康を第一に考え、靴は足を守る道具だとする師匠の目には、それらダメ出しをしてしまう靴は頭が痛い問題にしか見えなかったのです。
確かに靴は足のための「道具」です。
ただ、それだけではない側面も持っています。
だからこそ靴にはヒール靴、サンダル、ミュール、ブーツをはじめ様々なバリエーションがあります。

何だかこれじゃない感覚
靴を履いて出掛ける時にふと、何だかこれじゃない!と思うことはありませんか。
結局、靴に合わせて着る服を変えたりする場合もあります。
お客様からよくこんなお声を聞きます。
- 好みの靴が履けないからオシャレに自信がなくなった
- スニーカーしか履けなくてカジュアルな服ばかりです
- ヒール靴を履いている人が羨ましい
”服は第二の皮膚”
哲学をベースにファッションを分析する鷲田清一氏はそう言っています。
私は思っている以上に皮膚の感覚がアイマイだそうで、意外と自分と外界の「境界」が分かっていないそうです。自分と外の境界線は皮膚ではなく、もっと感覚的なものになると鷲田氏はいっています。
つまり、自分を外界と区別して認識するのが服の役割。
服を着ることで自分が確認できるようになり服は私達の第二の皮膚になります。
すると、服は単なる布から私自身になり私自身を表すものにもなっていき、そこにファッションが生まれてくる。
靴も全く同じです。
靴があるから足を感じられる。
靴を履いて、「何だかこれじゃない!」そう思う時は現したい自分と違っていて、無意識にそれを感じてしまうからです。
靴は単なる歩くための道具ではなく、自分を表現するためのもの。
つまり靴も第二の皮膚と同じで、自分自身になるのです。
でも、ヒール靴をはきたいけど痛くなるので履けない方がいます。
ヒール靴を履いてはいけないと思っている方もいます。
この解決はそんな複雑な事ではなく、むしろ単純だと思っています。
履けないなら、履ける足と身体になればいい。
それが自分を表す手段なのですから、むしろ履いていくべきだと考えています。

最近になって件の師匠は「女性がオシャレをしたいっていうのはしょうがないよね。私もずいぶん丸くなった」そう言っていました。(これはちょっと驚きでした^^;)
もしヒール靴を履きたいなら、履ける足になって、存分にヒール靴を履いていきましょう。
私はフットレスキューという肩書きで仕事をしていますが、単に足を健康にしていくだけが目的ではありません。多様化する靴に自分の足を合わせていく、それが自己表現で自分らしさなら、そこも含めてレスキューしていきたいと思っています。
そのために、自分の足を誰かに頼る事なく「健康」で且つ「美しく」していくためのメソッドをご用意しています。
ヒール靴が履きたい!なら、ぜひ『美健足レッスン』をお受けください。
美健足レッスンをお受けいただくにはまずは足の相談会、個別カウンセリングのどちらかへのご参加が必要になります。
足からあなたの未来を変える!足のお悩み相談フットケア専門のフットレスキュー井出淳子です。子供の時のケガのため15歳の時に医者から「将来、君は歩けなくなる」と言われ、20代は足の問題に苦しむ日々を過ごしました。自分自身の足の問題を解決するため足と体の勉強をはじめ、ボディケアの世界に転身。自分自身の体を実験台にさまざま行う中で得た経験を元に『美健足レッスン』というメソッドを考案。現在は中野駅北口に足から体を見直すサロン「ラポルト」にてフットケア、ボディケアをとおし皆さまの足の問題に向き合っています。目標は「天国の階段も自分の足でのぼる!」 一生ヒール靴でイキイキと歩けるよう頑張っています。